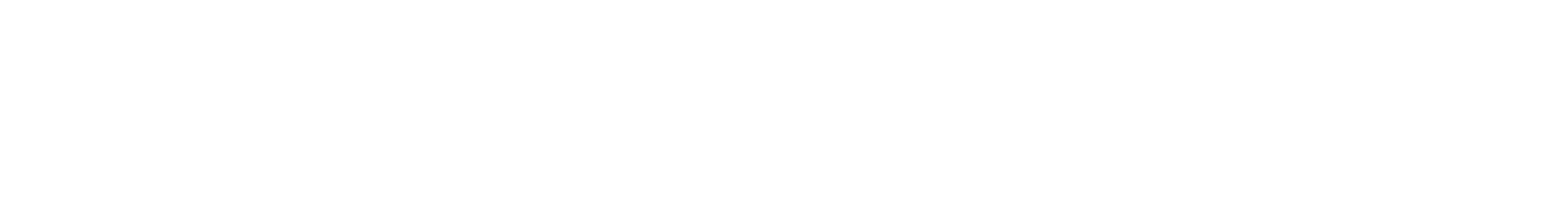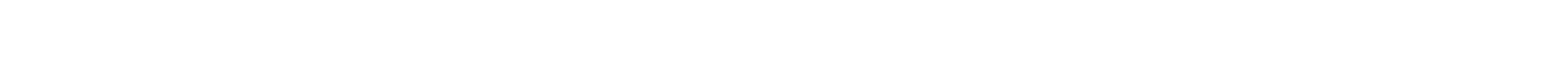September 2024
Vision Pro 2ヶ月使ってみた
2024/09/29 16:59 カテゴリ:Vision Pro
Vision Proが来てから、2ヶ月以上が経過しました。
visionOS 2もリリースされましたが、ここまでの使った感想やわかったことをまとめておきます。
◼️買ってよかったか
まず最初に結論、買ってよかったか、60万の価値があったか、ですが、買ってよかったですね。
60万の価値があったかについては、30万ぐらいまでは自信をもってあった、と言えそうですが、まだ60万の価値には、達していないかもしれません。
ただ、これからまだ使い方が進化したり、アプリやコンテンツも増え、OSも進化すると思うので、最終的に60万円の価値は超えそうな感触はあります。
◼️使い方
仕事では、まだ限定的にしか使えていないのですが、プライベートでは、Mac、iPadなどを使うほとんどの時間は、Vision Pro経由で使っています。
せっかく高いお金を出して購入したのですから、最初は意識してそうしてきたところもありますが、最近は習慣化してきて、被れそうな時は、Vision Proを被って、何かしよう、という感じになってきました。
1日の中でいうと、朝は、朝食のあとの運動タイムで、まず被ります。Zwiftというバーチャルのサイクリングアプリがあるのですが、これをVision Proを被りつつ、傍にYouTubeを流しながら、運動します。
シャワーを浴びて、仕事を始める前に、ゲームの日課を少し消化する時間があるのですが、その時も被ることが多いですね。家族が朝の情報番組などで、テレビを使っているのを邪魔しないように、かつ、自分もどうせなら、大きな画面でプレイしたい、というのがあるので、Vision Proは適任です。
この時に、運動とシャワーで上がった体温を扇風機でクールダウンしているのですが、Vision Proの仮想ウィンドウの向こうに扇風機を置いています。仮想ウィンドウなので、そのまま風が透過してくるのも、リアルなディスプレイにはない利点です。
仕事が終わったあとは、夕方以降の余暇時間の半分ぐらいは、Vision Proを被っているでしょうか。
その日によって違いますが、動画を見たり、テキストを入力したり、調べ物をしたりをソファに座りながら、Vision Proで行っています。
Vision Proは暗闇が苦手なので、寝る前には使い終わります。
平日はこんな感じですね。
◼️使い途
Vision Proを何に使っているのか、というところですが、主にこんな感じです。
原稿作成
ゲーム
動画視聴
仕事
動画作成
ブラウザ・メール・メッセージ
いずれもVision Proでなければ、できないことではありません。普通のMacや、iPad、iPhoneの用途と同じですね。
ですが、Vision Proを使うことで、効率があがったり、楽しく作業できたりなど、利点がありました。
Vision Pro単体か、他のデバイスとの組み合わせかでいえば、ゲームと仕事と動画作成は、iPadやMacとの組み合わせ、それ以外はVision Pro単体です。
想像通りですが、iPad Proでやっていた内容がそのまま、Vision Proに移ってきた感じです。必然的に、iPad Proの利用頻度は落ちました。
Vision Proならではの、MacやiPadなどよりも、より使いやすい用途としては、
楽譜を見ながら楽器練習
Zwift
があります。後でもう少し触れますが、画面を見たいけど、ちょうどいい場所に置くのが難しい場合ですね。
楽器練習にしろ、自転車にしろ、iPadなどでは、本体を置くための譜面台やら、ホルダーが必要になってきますし、それらを使っても、ちょうどいい場所にセッティングするのは、結構難しいわけですが、Vision Proなら、空間上のどんな位置にでも、必要な情報を固定できます。
ミュージックビデオ
音楽をききながらMacやiPadで作業する、というのは、誰でもすることかと思いますが、Vision Proだと、その時にミュージックビデオを流す、ということがやりやすくなります。
MacやiPadで作業をする際に、音楽だけなら場所を取らずにながら聴きできますが、ミュージックビデオを流そうとすると、映像のウィンドウが、限られたMacのデスクトップなどを占有してしまいます。
Vision Proであれば、作業領域は空間にたくさんおけるので、自分の目に入るところで、邪魔にならないところにも、ミュージックビデオの映像を置いてながら見しながら作業ができます。
◼️なぜVision Proを使うのか
これまでの動画でも繰り返し述べていますが、今回は、まとめの動画なので、あらためてVision Proを使う利点をあげていきます。
大画面
マルチウィンドウ、ディスプレイ位置、大きさの自由度、
作業場所の自由度
姿勢の自由度
Vision Proについて、Appleは、空間コンピュータという言い方をしていますが、自分なりに空間コンピュータをもう少し具体的にいうと、自由にサイズを変えられるウィンドウを空間の自由な位置に配置して作業できるコンピュータ、と言えるかと思います。
特にiPadとの比較で言えば、iPadでは、Split Viewや、ステージマネージャーを使って狭い作業領域の中で、なんとか複数の情報を扱おうとしてきたわけです。
Vision Proは、そいういった作業領域の狭さ、という制約を一気に取っ払うことができ、身の回りの空間の色々なところに、好き放題、好きなだけウィンドウや情報を配置できてしまいます。
iPadOSの、今までの苦労はいったい何だったのか、という気持ちになってしまいます。
また空間に自由に情報を配置できることによって、従来のMacやiPadに比べて、操作の姿勢や、場所の自由度がかなり高くできます。
整えられたデスクの前だけではなく、モニターアームなども必要なく、後傾姿勢でも、ベッドの上でもいいわけです
今、ちょうどこの動画の原稿を書くのに、ソファの上で、膝の上にMX Mechanical miniキーボードをおいて、顔の正面の空間にメモ帳のウィンドウを開いてタイピングしています。
この作業をMacBook Proでやると、ディスプレイの位置や大きさはベストなポジションではなく、膝の少し上となってしまいますが、Vision Proでは、一番みやすいポジションにウィンドウを置くことができます。
これが一つのウィンドウだけでなく、Vision Proの中には、複数のMac、iPad、iPhoneを表示できるので、今まで使い分けてきた色々なデバイスをVision Proの中で統合しているような感覚になります。
マルチにデバイスを使うということは、必然とマルチスクリーンになりますが、Vision Proは、マルチスクリーンの先にある統合ディスプレイ、という言い方がいいのかもしれません。Appleが製品名にVisionと名付けた理由も、さまざまなデバイスの見る部分を統合し特化したデバイスと考えると、なるほどな、と思っているところです。
◼️大画面ディスプレイとの比較
自分は、結構、大きな画面が好きな方で、Macにも40インチの5K2Kディスプレイを使っていますし、テレビも75インチのものを愛用しています。
リアルな大画面のディスプレイと比べて、Vision Proはその代替になるのか、という点では、発色やくっきりさでは、リアルなディスプレイに軍配があがります。
ですが、リアルディスプレイの80%ぐらいの感覚で使える、と思ってます。十分実用的な範囲ですね。
それに加えて、ディスプレイとの距離を自在に変えられる、どこでも配置できる、という外付け大画面ディスプレイにはない利点があります。
こういう利点があるのでMacの外部ディスプレイは、Vision Proで置き換えられると思っているのですが、不思議と75インチ4Kテレビは、あまり置き換えようとは思わないですね。
言語化するとしたら、テレビは、一番楽な状態で見られるディスプレイなので、Vision Proすら被りたくない時に使うもの、というのと、用途は、ほぼエンタメなので、より画質を優先したくなるから、でしょうか。
◼️Vision Proを使うならこんな人
自分がVision Proを使っている経験から、Vision Proを使う価値を感じそうな人をあげるとしたら、こんな感じでしょうか。
自宅、個室などで作業する時間が長い
iPadを便利に使っている
作業の多くがMacやiPadの中で完結する
Macで30インチ以上のモニタを使っている
ディスプレイアームで使っている
自宅、個室などで作業する時間が長い
Vision Proは、空間コンピュータというだけあって、空間に対して作業領域を展開するので、自分用の同じ空間を自分なりにカスタマイズして、長時間作業する人には利点が多いと思います。
自分用に確保された空間があれば、自分の必要なウィンドウを自分の好きな位置に配置して作業できます。作業を中断して戻ってきても、空間が維持されていれば、その状態のまま続きができます。
逆に一般的なオフィスなどの共同スペースで作業していたり、そこへ出入りが激しい人だと、他の人がウィンドウに被ったり、会話が発生して自分用の作業環境が崩れたり、出入りしている間に周囲環境が変わったり、配置を変更する必要が出たりと、面倒なことが増え、だったら最初から、一つのスクリーンでいいや、となってしまいます。
iPadを便利に使っている
Vision Proは、iPadOSをベースに作られているようなので、iPadを便利に使っている人にとっては、置き換えられる用途が結構あるので、価値を感じやすいと思います。
逆に、現時点でiPadを使っていない人、必要でない人、言い換えると、なんでもMacで済ましてしまう人や、iPhoneで十分という方ですね。こういう方は、Vision Proの価値の一部、特に単体でアプリを起動して使える、ハードで言えばM2チップが載っている部分は必要が無い可能性が高く、割高感を感じやすそうです。
そういった方はVision Proではなく、今後噂されている、下位グレードを待った方がよいかもしれません。
作業の多くがMacやiPadの中で完結する
世の中には、いろいろな仕事や個人的な作業、趣味があると思いますが、 その中でMacやiPadを使う割合が多いのであれば、Vision Proの恩恵を受ける時間も長くなります。リアル作業が多かったり、細切れな時間でMacやiPadを使っているのであれば、その延長線上にあるVision Proに対しても費用対効果は少なくなるでしょう。
Macで30インチ以上のモニタを使っている
これは大画面が好きとか、やっぱり大きな画面が必要、かつ、そこに投資もしているか、ということですね。
今、Macの外付けディスプレイのサイズで多く見かけるのは27インチや24インチぐらいでしょうか。これで何の不満も感じていない方や、ディスプレイの大画面化に投資効果を感じない方は、Vision Pro を検討しても、意義は感じにくいかなと。
もちろん、30インチ以上にしたいけど、スペースの都合などでどうしても置けないという方には、Vision Proは、価格は別として、解決策としては優れていると思います。
ディスプレイアームで使っている
こちらも大画面と同じ感じですが、ディスプレイアームを使う人は、ディスプレイの位置、配置について、改善したいということだと思います。
Vision Pro内のウィンドウは、あらゆるディスプレイアーム以上の簡単さで、ディスプレイの位置を調整できます。 、
以上、Vision Proを買う理由がある人は、こんな人かな、と思ったものを挙げてみました。
主にメインの作業環境がこうなっている、というのを挙げてみたのですが、Vision Proをすでに買ってしまった人は、コワーキングスペースや、フリーアドレスのオフィス、新幹線などの移動中や、出張先、旅行先など、作業環境が制限される場所でも、普段と同じような作業環境が構築しやすくなる利点がある、と付け加えておきます。
◼️やらないこと、やれないこと
今後のOSのアップデートで解消されることも多いと思いますが、自分が感じる、現時点でVision Proの苦手な点、不満点、向いていない点をあげておきます。
リアルと行き来する作業
他の人とのビジュアルコミュニケーション
iPhoneでのワンタイムパスワードが面倒
写真編集
リアルと行き来する作業
Vision Proには優れたパススルー機能があるので、現実を拡張してくれるMRデバイスという期待があると思いますが、実際には、パススルー映像として映し出される現実世界の解像度が圧倒的に不足しています。
Vision Proを被ったまま、リアル世界の作業をするのは、かなり難しいです。
飲み物を飲むぐらいの日常動作や、見ないでもできる単純作業ぐらいは問題はありませんが、Vision Pro越しに何か見て判断といった作業はほぼ諦めた方がいいでしょう。
またディスプレイを開くだけで使えるMacや、画面をスワイプするだけで使い始められるiPhoneに比べて、Vision Proは、頭に被る、という動作を挟まないといけないので、ちょこちょこ使ったり、外したりを繰り返す作業には向いていないですね。
一度被ったら、しばらく被りっぱなしにしていて、作業効率があがってくる、という使い方がむいていそうです。を
他の人とのビジュアルコミュニケーション
ゴーグルを被っているわけなので、対面、オンラインともに、他の人との表情を使ったコミュニケーションも諦めた方がいいと思います。ペルソナなどの機能はあるものの、質、機能も不足していますし、相手との合意も成立させにくいでしょう。
対面で会話する機会を設定した上で、Vision Proを外してコミュニケーションできるのに、外さないのは、相手に対して不必要なメッセージを発してしまいます。
今のところは、顔をみせる必要がある場面では、Vision Proを外す、以外の選択肢はないように思います。
もちろん、テキストメッセージや、音声のみのコミュニケーションであれば、Vision Proをつけていても何ら問題はないと思います。
iPhoneでのワンタイムパスワードが面倒
Vision Proには、OpticIDという生体認証もありますし、Apple Watchを使っていれば、iPhoneやMacの起動時の認証は突破できます。
ですが、iPhoneアプリの中のFaceID認証の時は、そのどちらも使えず、iPhoneのFaceIDしか使えません。
なので、パスコード認証にするしかないわけで、この辺は、仕事の環境へのログインや、FF14でもワンタイムパスワードを毎日結構な頻度で使っているので、不便です。
将来的には、生体認証がデバイス間でも共通化されるでしょうが、そこまでは我慢な感じです。
ケーブルはやっぱり邪魔
個人的な工夫で、Vision Proのハードウェア的な部分は、かなりカバーできてきたかと思いますが、ケーブルがでるというのはやはり不便です。
今は、純正バッテリーは頭にマウントしているので、このケーブルが外に垂れることはないのですが、バッテリー持続時間の短さをカバーするための外付けバッテリーを使っているため、そのケーブルが垂れています。
このケーブルを腰やポケットにいれていると、椅子の肘置きに引っかかったり、体と背もたれの間に挟まって頭を引っ張ったり、使い勝手が悪くなる原因になっています。
モバイルバッテリーを首から、社員証みたいにぶら下げると、ケーブルがどこかにひっかかる問題は、多少マシにはなりますが、バッテリーを大容量化して、頭や肩にマウントする方法を考えてもらいたいところです。
写真編集、というのは、いきなり細かい機能の話しになりましたが、Vision Pro上の写真アプリではトリミングすらできない、ということを言っています。
Vision Proを被ったまま作業を完結させたいのですが、写真やスクショを撮ったら、わざわざiPadやiPhoneを立ち上げたり、Vision Proの中に、iPhoneやiPadの画面を呼び出して、その中の写真アプリでトリミングしてから、iCloud経由で同期し、Vision Proで呼び出す、というなんとも面倒なことをやっています。
なんとかしてほしいところです。
◼️使うための工夫
Vision Proは非常に高価ですので、単体で完成された状態であってほしい、買ったらそのままの状態で最高の使い勝手であってほしい、というのは自然なものだと思いますが、実際にはそうではありませんでした。
ですが工夫や追加投資で、解決可能なものもありますので、それをまとめておきます
装着性
バッテリーの持ち
入力デバイス
Air Pods
作業場所
装着性については、何回か動画を出していますが、簡単にまとめると、そのままでは顔が痛くなるので、長時間作業ができない、というものです。
解決策は、バッテリーを後頭部に取り付けることでバランスを改善、ストラップ類をつけることで、顔面への圧迫をなくす、ということになります。
今のところは、自分は、AnnaProと面ファスナーを使うことで快適環境を作れています。
バッテリーの持ちについては、モバイルバッテリーを複数用意して、ローテーション運用することで、解決可能です。これも動画を作成しています。
入力デバイスですが、Vision Proは、視線とジェスチャという新しい入力方法を採用していて、これはかなり直感的で便利ですが、作業の内容によっては精度が足りません。
また、テキスト入力が必要な作業については、Vision Pro単体では、実質的には無理です。
Macで閉じた作業をする場合には、Macについているキーボードやトラックパッドを使えますし、Vision Proにも、外付けキーボードとMagic TrackPadを接続できますので、これらを使うことで、MacやiPadと同様に作業ができます。こちらも動画を作成しました。
visionOS 2から、マウスも使えるようになりました。トラックパッドの場合は、操作をするには、どこかに置いてから、操作する、というアクションが必要ですが、マウスの場合は、掴んで持ち上げて移動しつつ、そのまま操作できるので、Vision Proには合っているかもしれません。
ジェスチャが便利なのは、ウィンドウの移動、拡大縮小、スクロールとかですね。
おおまかに動かすときは、非常に直感的に動かせます。
一方苦手なのは、小さいオブジェクトをポイントしてクリック、タップ、ドラッグ。ここは、マウスやトラックパッドを併用したいところです。
AirPodsですが、Vision Proが、現実世界の上にウィンドウを重ねられるの同様に、AirPodsがあると、音声を重ねられます。
内蔵スピーカーもありますが、現実世界の音声を遮断したり、Vision Proの音声を現実世界に垂れ流さないようにすることもできるので、使い方の相性はかなりいいです。
作業場所ですが、コロナなどで自宅作業に移行した人は、自分の快適な作業空間を構築してしまったと思います。その快適な作業空間がすでにある状態では、Vision Proを使う必然性はかなり薄くなると思います。
Vision Proは、その快適な作業空間を維持・構築せずとも、別の場所や姿勢で似たような快適な作業空間を作れる可能性があります。
移動可能な机、椅子
自分の場合は、デスクは横においておいて、椅子のタブレットスタンドや、肘置きを工夫することで、デスクありきのPC環境とは違った観点で、Vision Proにあった作業空間を作れそうな気がしています。
また、折り畳みデスクなどを使って、今までMac作業をしていなかった場所でも、キーボードやマウスを置いて、作業しやすくできそうです。
◼️いらなくなるもの
Vision Proがあると、いらなくなるものがあるかも、ちょっと考えてみました。
自宅用iPad
PSポータル
1人用プロジェクタ
MacBookを買い替えるなら13インチでいい
外部ディスプレイ
まず、自宅用iPad。
Apple Pencilを活用している人は別ですが、自宅で使うiPadの用途は、Vision Pro でほとんど置き換えることができます。今は、まだVision Proで使えないアプリがありますが、対応が進むと、iPadを使う場面は、かなり減ります。
Vision Proをゲームで使う、という動画もアップしましたが、PS5のゲームを家の中でどこでも遊べるPSポータルの機能も代替できます。
かなり直接的におきかえるのは、ひとりで大画面を楽しむためのプロジェクタ。家族で楽しむ大画面は置き換えられないですが、自分だけで楽しむ分には、音声も含めて、Vision Proの方があらゆる面でいいです。
いらなくなるもの、とは違いますが、今自分は16インチのMacBook Proをメインマシンにしていますが、次にMacBookを買う時は、小さい方のサイズを買うと思います。
Vision Proを被れば、どこでも16インチどころではないサイズを扱えるわけなので、そこのコストを追加で払う意味は感じないです。
同じようなことですが、今40インチの外部ディスプレイを使っていますが、壊れたとしたら、外部ディスプレイ自体を買わないかもしれません。少なくとも30インチ以上のディスプレイは買わないでしょうね。
◼️Vision Proが向いていないひと
ここまで自分は、Vision Proはこんなふうに使ってます、という話しをしてきましたが、客観的にみれば、これらに当てはまる人は、少数派だろうな、とは思っています。
逆に、Vision Proをいらないとか、魅力を感じない人ってこんな感じだろうな、というのをまとめてみました。
PCなどで作業が完結しない人
単一デバイスの人
情報量が少なくていい人
リアルとの行き来が多い人
周囲の人と直接のコミュニケーションをしながら作業する人
大画面の迫力に魅力を感じない人
デスクを整えるのが好きな人
要は、今まで挙げたことの逆のことになります。
こうやって挙げてみると、こういう人の方が多数派だろうなと思いますね。Vision Proが少なくとも現段階では、爆発的な普及をしそうにない理由でもあると思います。
◼️仕事での利用
Vision Proで仕事ができるか、という点について、前の方で、限定的にしか使えていないと言ったのですが、
その原因となるのは、顔出しのオンラインミーティングが、ところどころ不定期にはさまってくるからです。
仕事はMac2台をつかってやっているのですが、ひとつひとつの作業は、Vision Proを使って作業する方がちょっと効率的だったりします。
ですが、ミーティングが挟まると、その度に、Vision Proを被ったり、外したり、という作業が発生します。
30分後に、またミーティングだから、外した状態で作業を続けるか、みたいなことが繰り返されて、結局、Vision Proを使わなかった、ということになりがちでした。
ならすと、効率があがらないので、結局、仕事ではあまり使わない、ということになってしまっています。
これはVision Proの性能、機能が足りない、ということではないので、あまり改善する方法がない気がします。ミーティングを午後に集中させて、午前は被りっぱなし、ぐらいでしょうか。
動画作成などの、プライベートの作業であれば、そういったミーティングが挟まることもなく、一人の作業なので、ずっと被ったままで最初から、最後までできるようになってきました。
◼️VR/ARデバイスなのか
Vision Proが空間コンピュータである、という点は、ここまでの話しで、ある程度説明できた気がしますが、なぜVR/ARデバイスとは呼ばないのか、について自分なりの考えを共有します。
VRは仮想現実、現実には存在しないものを現実として感じる、
ARは拡張現実、現実に存在するものに対して、存在しない情報などを付加する、
と簡単に定義しておきます。
どちらもリアリティという言葉を使っていますが、Appleは、Vision Proでは、コンピューティングの中では、この「リアリティ」を意識しないようにしているように見えます。
Vision Proが、空間コンピュータとして実現しているのは、昔からある、MacやiPadアプリのウィンドウを現実空間と重ねて表示する、ということですので、そこに新たなリアリティは存在しません。
仮想とか、現実とか、リアリティなどと関係なく、今までのアプリやウィンドウが便利に使える、というだけです。
あくまで、AppleがこれまでにMacやiPhone、iPadで作ってきたコンピューティングの延長線上にVision Proは置かれているわけです。
VRは、現実の空間と切り離される一方で、実際の生身の体は現実に置かれています。
現実世界に生身の体を置きながら、仮想現実で視野を覆うことは、基本的には体を危険な状態におきます。そういった危ない状態をコンピュータの主要な用途と位置付けるのは、ユーザーにリスクを強いてしまいます。
Vision Proには、今までのヘッドマウントディスプレイと比べて、高品質のパススルー機能が搭載されています。このおかげで、生活空間を自由に行き来し、その空間のあちこちの場所で、自分の必要なアプリケーションやコンテンツを利用することができます。
一方で、QuestやPSVRなどは、セーフティエリアという形で、ユーザーを危険から保護しますが、ユーザーに空間の自由度はありませんし、セーフティエリアが作られなければ、操作すらできない、ということもあります。
Vision Proを使うことで、視覚を遮るVRは、体の危険や自由度と隣り合わせだった、ということを再認識させられました。
ARについては、VRのような身体の危険があるわけではありませんが、現実を補佐できるほど、Vision Proのカメラ映像は解像度がないため、諦めざるを得なかったのでしょう。
解像度を高めると、遅延が発生して、酔いの原因になったり、発熱やバッテリー消費につながって、実用性が減ったりするわけなので、望まれる用途ではありながらも、現在の技術では、メインの用途としてはARは実用が難しい気がします。
VRもARも、視覚にフォーカスしたウェアラブルデバイスのメイン用途として使えない、一方で、自社には連綿と培ってきた、2DベースのOSと、アプリやコンテンツ、それらを使うユーザーの資産がある、となればAppleが打ち出す方向性は、3D空間に自由にウィンドウやアプリを配置できる、空間コンピュータだった、というのが、今のVision Proの位置付けなのかな、と思いました。
Vision Proは妥協の産物という言い方もできますが、将来に向けて、用途や技術を発展させるためには、どこかのタイミングで現実の製品をリリースしないといけない。
そのポイントがようやく来た、と捉えています。
◼️3Dコンテンツの道は険しそう
Vision Proは、2Dベースのウィンドウを3D空間に配置するコンピュータとしてスタートしましたが、当然、3Dベースのアプリやコンテンツは、これから登場することが、期待されているところだとは思います。
ですが、実際には3D空間をフルに活かしたようなコンテンツが拡大するには、かなりの時間がかかりそう、というのがVision Proを実際に手にした後の感想です。
iPhone 3Gが日本で登場した時の価格は2.3万円で、そこからスマホの普及率が10%に達するのに2年、50%に達するのに4年かかっています。
当時を思い出すと、これからは携帯デバイスはこの方向だと、多くの人が気づいており、環境がまだまだ整わない中、iPhoneに合わせて、アプリやシステムが、ものすごい勢いで開発され、リリースされていきました。
一方、Vision Proは、開発環境などは、iPhone登場の頃とは比べ物にならないほど整備されているにもかかわらず、Vision Pro用の新しいアプリの登場は、非常に遅いペースです。
Vision Proの登場時価格がiPhone 3Gの26倍と、大きなハードルになっていることで、ユーザーの増加ペースが遅いこと。
おそらくVR/ARといった、従来型のヘッドセットデバイスのxRの文脈では、狭い専門的な領域は別として、Vision Proでやりたいこと、やるべきこと、やれることが見つかりにくい。
Vision Proの発表時には、M2チップが搭載されていることで、性能的には十分かと思いきや、両目で8Kをリアルタイムで描画するような3Dコンテンツは、M2チップでは荷が重そうです。
市場が小さい、用途がはっきりしない、パワーも不足していて振り切ったものも作りにくい、ということで、開発者も舵を切りにくい、となっていそうです。
個人的な読みとしては、Vision Pro用の3Dコンテンツは、iPhoneが2年で達した水準に、10年経っても到達しないのではないかと思いました。
一方で、Apple TVなどで提供されている、3D映像、イマーシブビデオの分野であれば、高解像度の映像を流すだけなので、これ以上のチップ性能などは必要なさそう。なので、3D映像の分野は今後、充実していく可能性は高そうです。
◼️廉価版Apple Visionの予想
廉価版Apple Visionが登場すると予想されていますが、どこをコストダウンするのかといえば、個人的には、Macや、iPad、iPhoneと連携して、空間にそのデバイスのウィンドウを表示する機能だけに特化する、という線なのではと思っています。
今あるようなVision Pro専用アプリは、廉価版では使えないのでは、という予想ですね。
Appleデバイスでの、3Dをフル活用したVRのようなコンテンツの普及はより見込めませんが、その辺りはMetaに任せる、ということなのかもしれません。
一方で、Mac、iPad、iPhoneで、Apple Visionと接続したときは3D立体視できるような対応アプリ、というのはでてくるかもしれません。
この場合も、あくまで処理はMacなどで行われて、Apple Visionは、3D表示だけを担当する感じでしょうか。
そういえば、もうすぐvision OS2で、Mac仮想ディスプレイがワイド化されますが、同じ技術で、3D立体視用の映像をMac側から送ることができそうですね。
この流れも今後のApple Vision の位置付けに影響しそう。
こんなふうに廉価版Apple Visionで3D表示や、空間コンピューティングに慣れてもらう間に、Vision Proで、ゆっくりとVRなどのフル3Dアプリを増やしていくという流れになりそうな感じがしています。
◼️まとめ
非常に長く、後半は、個人的な妄想でしたが、ひさしぶりのAppleの新カテゴリデバイスということで、色々な刺激がありましたし、自分の作業環境も大きく変わり、便利に楽しくなったのは、間違いないかと思います。
Vision Proを2ヶ月使って、その本質的な価値は、Appleデバイスの画面を空間に統合すること。一方、VR/ARなどは、まだまだ難しいよね。というのがまとめになります。
VisionPro装着感改善ANNAPROでいいのかも
2024/09/16 16:57 カテゴリ:Vision Pro
いままで、Vision Proの装着感を改善するものとして、BOBO VR、ソロニットバンドについて動画をアップしてきましたが、その後、さらにいくつか試してみたことを共有します。
結論としては、今のところANNAPROというところのVision Pro用ストラップでいいのでは、という感じです。
AirCover 2.0
BOBO VR導入後に、Vision Proの装着感を改善するために買ったアクセサリは3種類あるのですが、まず最初はInfinity One というところのAirCover 2.0です。
AirCoverを知ったのは、YouTubeとかでおすすめ動画に出ていたのだと思うのですが、特に欲しいと思ったわけではありませんでした。
買うつもりはなかったけど、海外の商品のようだったのでApple Payで送料いくらかな、とみようと思ったら、注文が通ってしまっていました。完全に事故購入ですね。
3Dプリンタで作られたものらしく、高級感とか全くないのですが、本体価格はものの割には高め、さらに日本までの送料が3000円ぐらいと、めちゃくちゃ高いです。
AirCoverはどういう商品かというと、Vision Proのライトシーリングの代わりとして使うもので、純正が顔面に全体的に接触するのに対して、AirCoverの場合は顔面との接触面は、おでこの上の方に限定されています。
なので、純正のライトシーリングと違って、顔の横、ほおのところが解放されていて、その点の圧迫を感じなくなっています。ムレがないのもいいところ。
加えて、左右には、隙間を隠す別パーツがあるために、ライトシーリングを使わないのに没入感は少し高くすることができます。
AirCoverの取り付けは、SIMピンなどを使って、Vision Proの左右のアームを取り外して、AirCoverを差し込み、アームを戻します。
戻したあとで、左右のカバーを取り付けます。
バッテリーを後頭部にマウントして、前後の重量バランスを取っている前提で、純正のライトシーリングよりも快適なことは間違いありません。
ですが、顔面に分散していた重量が、おでこ上部に集中することもあり、2時間ぐらいが限界な気がします。
純正のライトシーリング単体だと、自分の場合は30分も持たないので、それよりも大分といいのですが、前後に挟む方式だけでは、快適な装着、というにはやはりちょっと難しいかもしれません。
ノーズパッド
次に試してみたのが、しのぶ工房のノーズパッド。
YouTuberの方が紹介されていたので、即、購入してみました。
モノとしては、Vision Proのレンズの間に装着して、メガネのように鼻で支えるものです。
紹介した人の補足によると、これは単体で使うよりも、先ほどのAirCoverのように、他に頭などに重量を分散させる方法と併用するようです。
鼻に当たる部分はあるものの、自分はメガネ歴が長いので、メガネと同様の形式であれば、あまり違和感を感じないのでは、と注文してみました。
これも3Dプリンタで作られたモノですが、価格はめちゃくちゃ良心的で、注文後すぐ到着しました。
取り付けは、Vision Proの真ん中内側にひっかける形で装着。鼻に当たる部分には、スポンジが付属していましたが、このスポンジは触り心地も悪く、面で鼻と接触する形になっていて、違和感がありました。
なので、Amazonでメガネ用のシールで貼ることのできる鼻パッドを購入して、取り付けています。
実際の使用感ですが、最初、AirCoverと併用してみたのですが、オデコと鼻のバランスが取れれば、かなり楽になりました。
AirCoverだけだと、2時間が限界でしたが、ノーズパッドをつけることで、時間での限界はなくなったかもしれません。
難点を挙げるとすると、Vision Proのガラス面を保護するTPUのカバーと干渉するところでしょうか。
無理して併用はできますが、実際にケースが役立つ場面は何回もあり、ガラス面は保護したいところなので、ちょっと気になるところです。
Anna Pro
最後に試してみたのは、ANNAPROというストラップです。
これはVision Proの左右のアームの間を渡す樹脂製のストラップになっていて、内側にスポンジを取り付けることができます。
調整機構などはなく、スポンジの厚みが2種類付属します。
取り付け時は、ソロニットバンドは外す必要がありますが、アームは外す必要はありません。
先に買ったAirCoverとは、頭と接触して保持する場所が、微妙に違うので、同時に使うこともできました。
購入の目論見としては、AirCoverとノーズパッドで分散した接触箇所をさらに分散させることで、一箇所にかかる圧力を減らすことができるのでは、というところです。
で、いろいろ試した結論ですが、AirCoverやノーズパッドを使わずに、ANNAPROと面ファスナーを組み合わせたセッティングが一番よさそう、ということになりました。
まずノーズパッドですが、鼻に接触すること自体は慣れているので耐えられるのですが、無接触であればそれに越したことがないわけです。
ノーズパッドを外して、AirCoverとANNAPROだけにしてみたところ、確かに頭にかかる重量は増えるものの、許容範囲だったので、であれば、カバーとの干渉も気になるので外してしまうことにしました。
ANNAPROとAirCoverとの併用ですが、確かに圧力は分散になっていました。
ただ、2つ使うので重量が増えているのも気になるので、ANNAPRO単体なら、意外といけるのでは、となりました。
一方で、ANNAPRO単体だと、BOBO VRなどと違って、位置や締まりを調整できないし、あまりフィットせず、ずり落ちる感じが気になります。ずり落ち感をなくすには、ソロニットバンドをかなりぎゅっと締めることになって、頭が痛くなります。
そこで、結局いつもの面ファスナーの投入。
縦方向に調整可能な面ファスナーを加えることで、ずり落ち感を軽減。
同時に、2本の面ファスナーがおでこにかかっていた圧力を分散。
面ファスナーの長さで、ベストセッティングをある程度固定できるので、装着時のセッティング作業の時間短縮となりました。
このセッティングであれば、ソロニットバンドのダイヤルは完全に緩んだ状態でも使うことができ、前後の圧迫も頭の締め付けもほとんどありません。
◼️違い
AirCoverとANNAPROは似たような仕組みですが、違いは、頭のどの部分で接触しているか、という点。
AirCoverはおでこの皮膚部分で接触しているのに対して、ANNAPROはおでこの上の髪の毛がある部分で接触しています。
AirCoverだと、前後の締めつけでVision Proを固定するのに対して、ANNAPROは、もう少し頭の上側にあるので、前後ではなく頭の上に載せる形になります。
またAirCoverは、おでこで支えるため、皮膚に直接接触する部分が多く、接触面がヒリヒリして来て、耐えられなくなってきます。
ANNAPROの場合は、おでこの上の髪の毛のある部分で接触するので、ヒリヒリはなりにくいですね。帽子を被っている感覚です。
装着感
完成したセッティングの付け心地ですが、BOBO VRの、頭に載っけておくだけでいい、というラフな感じには及ばないものの、かなり近いところまではきていると思います。
逆に、フワフワした感じはなく、適度なフィット感があるので、大きめの動きがある時でも、安定して装着することができます。
装着方法ですが、まずソロニットバンドのダイヤルは完全に緩めて、伸びる状態にしておいてから、前髪をあげながらANNAPROのスポンジ部分に頭をあてます
その後、バンドやバッテリー位置を調整。
自分の場合は、そのままではVision Proと顔の距離が遠くて、アラートがでてしまうことが多いので、ソロニットバンドのダイアルを結構締めて、OpticIDの認証を突破します。
そのあとは、ダイヤルを適度に緩めて、楽な状態で使っています。
ライトシーリング
ANNAPROとAirCoverは併用できるわけですが、純正のライトシーリングも併用できます。
シーリングの周りのクッションをつければしっかりホールドでき、隙間もありません。
クッションを外すと、隙間はできますが、顔に密着しなくなるので、むれや圧迫はなくなりつつ、そこそこの没入感になります。
AirPods Maxとの併用が可能
BOBO VRと比べて、ANNAPROの利点は、AirPods Maxが使えることです。
BOBO VRだとフレームに厚みがあるので、AirPods Maxと干渉してしまうのですが、ANNAPROの場合は、ソロニットバンドを使うので、干渉せずに使うことができます。
AirPods Proは、そういったフレームの干渉問題はないのですが、AirPods Maxの方が、バッテリーが長時間もつので、Vision Proで長時間作業する時には、バッテリーを気にするものをひとつ減らすことができます。
セッティングととりつけ
面ファスナーのセッティングを紹介しておくと
ソロニットバンド側を保持するループを2本
調整ができるようリングを取り付けておきます。
ANNAPRO側にもループを2本取り付け、リングを出しておきます。
ANNAPROを取り付けます。
ANNAPROは、バンドが外れていれば差し込むだけで取り付けられます。
ソロニットバンドをとりつけます。
前後ろのリングができているので、これを面ファスナーで繋ぎます。長さは仮なので、緩めにしておきます。
ここで一度被って、VisionProが正しく動作するようにします。
被った状態のまま、面ファスナーを締めます。ポイントは、Vision Proが持ち上がるほどには締めすぎず、そのままの位置になるぐらいに締めるところです。
長さが調整できたら、バッテリーをとりつけます。
バッテリーは、ソロニットループの真上に付けてしまうとワークチェアのヘッドレストなどに当たってしまうので、少し上側にぶら下がる感じで付けます。
再度被って微調整すれば完成。
今のところ3週間ぐらい使っていますが、バッテリーの取り付けが少しグラグラするぐらいの不満点だけなので、しばらくはこれが一番いいかなと思っています。
ANNAPRO自体は、手軽でいいのですが、角度や締め付け具合を調整できないので、その辺が改善されるともっといいかな、と思っています。
※商品リンクにはアフィリエイト広告を利用しています。
■商品紹介
↓ANNAPRO Vision Pro用のヘッドストラップ
↓Air Cover 2.0 para Apple Vision Pro
↓Apple Vision Pro用 ノーズパッド Nose Pro
Vision Proを本格キーボードで使う
2024/09/14 16:53 カテゴリ:Vision Pro
今回は、Vision Proと合わせて使うキーボードとして、ロジクールのMX Mechanical Miniを導入してみましたので、合わせて使った感想などを共有したいと思います。
Vision Proとキーボード
Vision Proの使い方も大分慣れてきて、この動画などの原稿作成なんかにも結構使えるということがわかってきました。
今までは、Vision Pro用のキーボードとして、折りたたみキーボードのMOBO Keyboard 2を使っていました。
Vision Pro に合わせて移動して、いろいろな場所で使うには、コンパクトで持ち運びやすくていいのですが、長時間タイピングするには、若干使いにくいところもあります。
Macの方では、この4年ぐらいはロジクールのMX Keysを愛用しているので、Vision ProでMac仮想ディスプレイを使う時には、MX Keysを持ってきて使っていました。
ですが、Vision ProでMac作業をするたびに毎回キーボードを移動するのは、ちょっと面倒になってきたので、Vision Pro用に本格的なキーボードを導入することにしたわけです。
キーボードの候補は、同じMX KEYSの MINIか、メカニカルスイッチを採用したMX Mechanical Mini、あとはKeychronのワイヤレスタイプのものも考えていました。
それ以外にも、今、話題になっている分割タイプのキーボードが、実はVision Pro に合うのではと思っているのですが、Bluetoothに対応したJIS配列で手軽に入手できるものが見つからなかったので、今回は候補から外しました。
買ったのは
最終的に選んだのは、MX Mechanical Mini。
選んだ理由のひとつは、Vision Proと関係ないところですが、最近話題になっているメカニカルキーボードも一度体験してみようということ。
メカニカルキーボードの中では入門的な感じのKeychronにも興味があったのですが、重量が1.7kgとかあって、Vision Pro用と考えると重すぎると思い、候補から外しました。
Keychronを購入するならMac用として考えた方が良さそう。
なので残りは、MX Keysのminiか、Mechanical Miniということになります。
MX シリーズの共通の特徴は、3台までのデバイスに接続できて、Mac、Windows、iPadにも対応しています。
Vision Proと合わせて使う、という言い方をしていますが、Vision Proと直接ペアリングして、Vision Proアプリだけで使うだけではなく、Macとペアリングした状態で、Mac仮想ディスプレイで作業するときにも使うので、Vision ProとMacを簡単に切り替えて、Macに直接キー入力できるMXシリーズは、都合がいいわけです。
MXシリーズの中でも、Vision Proと組み合わせるなら、コンパクトさ優先で、テンキーはなくていい、ということでテンキーレスのminiタイプ。
せっかくなので、MOBO keyboard 2との差別化する意味もこめて、メカニカルタイプにしてみました。
接続
MXシリーズは、3台までのデバイスと接続できますが、自分の場合は、
1.プライベートMacBook Pro
2.Vision Pro
3.仕事用Mac Mini
という接続にしてみました。
MX Keysは、3つのデバイスを切り替えるために専用のスイッチが用意されていましたが、miniの場合はF1-3がそれぞれデバイス切り替えに割り当てられていて、長押しでペアリング、短押しで切り替えになっています。
重さ
今まで使っていたMOBO Keyboard 2は、286gだったのに対して、MX Mechanical Miniは612gと、2倍以上重いですが、主に家の中で使うことを想定しているので、持ち運べない重さではない感じです。
タイピングのしやすさ
話題のメカニカルスイッチのキーボードを使ってみたかった、と前に言っていたのですが、メカニカルスイッチのキーボードを初めて使った、というわけではありません。
自分が子供の頃NECのPC-80/88/98シリーズなどを使っていましたが、当時の主流はメカニカルスイッチだったと思いますし、自分が最初に使ったMacである、Macintosh Plusもメカニカルのようでした。
いつ頃からメカニカルタイプのキーボードを使っていないのか、もうわからないですが、キータッチは久しぶりの感覚ですね。NECのパソコンは、もっとカチャカチャしていた記憶なので、MX Mechanical Miniのスコスコした感じは、どちらかというとMac Plusに似ているかもしれません。
新鮮というより、懐かしい感じがしました。
愛用していたMX keysは、メンブレンだそうですが、キータッチそのものは結構好きでしたので、最初は慣れないかなとも思ったのですが、40年以上タイピングしているので、特に問題はなさそう。
逆に、一度体験するとメカニカルじゃなきゃいやだ、とかまではなる感じもなかったです。これはこれ、という感じ。
配列
配列は、エンターキーの外側に一列あるタイプですが、小指を伸ばしたとこにちゃんとエンターキーや、Back spaceもあるので、特に問題なく使えそうです。
一点だけ気になるのは、変換キーの位置が右すぎる点でしょうか。
フルサイズのMX keys は、Mキーのすぐ下に変換キーがあるのに対して、MX Mechanical Miniは、隣のカンマキーの下になっています。同じ、MXシリーズで統一してほしいところですし、正直そんなにスペースキーは長くなくてよいと思います。
日本語、英字混じりの文を打つ時には、変換キーはめちゃくちゃ押すので、ここはちょっと気になりますね。思った感覚よりも、1キー分右を押すことを意識しておく必要があります。
機能キー
Vision Proとの組み合わせでは、一番上段の機能キーで、使えるものと使えないものがありました。
使えるのは、再生ボタン、音量調整ボタン、ミュート、検索、音声入力
使えないっぽいのは
スクリーンキャプチャー、絵文字、マイクミュート
でした。
バックライト
MXシリーズには、キーボードを白く光らせるバックライト機能があります。
最初はあまり必要ないかと思っていたけど、Vision Proのカメラ越しにみると、解像度が低いのでキートップの文字がかなり見えにくくなります。
これが、バックライトをオンにするとよくみえるようになり、とくに伸ばし棒や数字など、遠いところや、あまり慣れていないキーを入力する時には、誤入力が減りました。
ちょいDIY
MX Mechanical Mini自体は、結構気に入ったので、Vision Proで使いやすくするために、少し椅子に工夫をしてみました。
自分は、エルゴヒューマンのワークチェアを愛用していますが、オプションのタブレットスタンドを装着してます。
タブレットスタンドというぐらいなので、キーボードを置いて使うことは想定されておらず、結構奥に位置しています。
これをキーボードで使いやすくするために、手前に少し出せるようにエクステンションを作ってみました。
5mm厚の塩ビの板を適当な大きさにカットして、両面テープで貼り合わせ段差を作ります。
あとは金具も両面テープで貼り合わせて、タブレットスタンドに引っ掛けるようにしています。
タブレットスタンドは、タブレットがみやすいように斜めになっているので、そのままキーボードを置くとずり落ちてきます。このエクステンションでは、貼り合わせてつくった段差の部分に、キーボードが引っ掛かるようになっているので、斜めになってもズリ落ちて来ないわけです。
肘置きはかなり調整が効くので、肘と、手のひらで支えるようにセッティングすれば、かなりタイピングしやすくなりました。
また、市販の肘置きに取り付けるタイプのマウステーブルも取り付け、ここにMagicTrackPadをおくことで、ポインタも操作しやすくなりました。
Vision Proを使うことで、今までのPCの使い方と違うことができないかと思っていたのですが、机を使うことなく、椅子だけで大画面を活かしたコンピューティングができるのは、Mac単体を超えた使い方にたどり着いた気がします。
Vision Pro単体で文章を作成する時は、肘置きのマウステーブルにMagic TrackPadを置くわけですが、Macに接続して作業する時は、トラックパッドの代わりに、Mac用のMagic Mouseをおき、MX Mechanical Miniは1番のスイッチで、Macに切り替えて使うことになります。
Vision Proに本格キーボード
空間コンピュータであり、視線とジェスチャで操作できるようになったVision Proに、原始的な入力装置であるキーボードを用意するというのは、時代に逆行する感じもなくはありませんでした。
ですが結局、現状、PCで生産的な活動をするには、キーボードは必須なわけで、Vision Proで生産性を確保しようと思えば、一定クオリティ以上のキーボードと組み合わせるのは、必然だったかもしれません。
逆に、キーボードなしに生産的な活動ができるか、と言われても、手足を縛って泳げと言われているような感じかもしれません。
キーボード、マウスを使うのであればMacだけでいい、という意見もあるかもしれませんが、もちろんそれでもできなくはないのですが、Vision Proは、作業場所、姿勢の自由度、同時配置ウィンドウの数、大きさ、配置場所の点で、Mac単体での作業よりもかなり効率的だと思っています。
というわけで、Vision Proに本格キーボードを合わせる、という試みは個人的にはうまくいったと感じてます。
Naya Createに期待
いったんこれでVision Proでの快適タイピング環境はできたと思ったのですが、XでNaya Createなる新しいキーボードの情報が回ってきました。
これまた最近話題の分割キーボードで、無線、iPad対応、JIS対応ができるようです。iPad対応ということは、同じ系統のOSであるVision Proでも使えそう。
最初に分割キーボードで、希望のスペックのものが見つからないと言っていたのですが、このNaya Createは該当しそうです。
分割キーボードに注目していたのは、先ほど、タブレットスタンドにキーボードを置くということをお見せしましたが、分割キーボードであればタブレットスタンドを使わずに、肘置きにキーボードを分割して置くことができます。
座ってそのまま楽な姿勢でタイピング、となるわけです。
今は、Magic TrackPadを肘置きにおいて使っていますが、Naya Createはオプションでタッチパッドを装着でき、キーボードとタッチパッドを両方使えます。
価格はかなり高いのですが、思い切って注文してみました。
ただ、注文してから気づいたのですが、到着は来年の8月予定だそうです。1年も待たないのといけないのと、それまでに、他のメーカーから、もっと格安の同じようなものがでるのをちょっと恐れています。
※商品リンクにはアフィリエイト広告を利用しています。
■商品紹介
↓ロジクール KX850CL MX MECHANICAL MINI
↓肘置き用マウステーブル
↓Apple Magic Trackpad